| 美土里陶房 | ||
交通アクセス
 |
||
| オーナー橋本修一・美代子夫妻 | ||
陶芸の里
| 光市室積の伊保木という地区に、陶芸の里が出来てかれこれ20年以上になるだろうか。 光市光井のスポーツセンター内にある窯で、趣味から始めた陶芸教室の生徒が独り立ちし、過疎で人口の流出が進んでいた伊保木の空き家を購入して始めたのが陶芸の里のそもそものはじめだとか。 そして今では、美術展で数々の賞を戴くほどの技量を持ち、光市は勿論、周南市でも個展を開いたりしている。どちらの窯も陶芸教室の生徒を持ち、年に何回かのイベントを行っている。 毎年2月の第一金・土・日曜日が陶びな展で美土里陶房と椿窯の共催となっている。この日は、美土里陶房が桜餅、椿窯がぜんざいを接待し、ここに来る客に振る舞っている。 そもそも陶びなは椿窯の主である上田氏が、我が娘のために「たたらびな」を作ったのが始まりだと聞いている。私にも3人の娘の子がいるが、ここでたたらびなを購入して、通い始めたのが10年前位だろうか。(定かではない)。今ではいろいろな種類の陶びなを制作し、毎年ここに来るのが楽しみになっている。(男だというのに変でしょう)。ここに来る目的は、陶びなを見る楽しみもあるが、酒器やその他の器を買ったりすることでもある。 そして、5月の最後の土・日曜日が椿祭り。この2つの窯だけでなく、近くの快山窯をはじめ光市の窯元が一堂に会し、焼き鳥屋や焼きそば屋、その他いろいろな出店が出て、それはそれは大いに賑わうイベントでもある。 10月の中旬の土・日曜日には、美土里陶房の生徒さんの集まりである「きみどり会」(まだみどりになれないから命名されたとか)の作品展がメインの「わいわい祭り」がある。 イベントがある日は勿論ですが、ない日も行けば何らかの収穫があるはずだ。また、空きがあれば陶芸教室の生徒にもなれるはず。一度覗いてみてはいかがでしょうか。 |
| 美土里陶房 | ||
交通アクセス
 |
||
| オーナー橋本修一・美代子夫妻 | ||
| 陶びな展会場入り口 | 陶びな展会場 | いろいろな陶びなの展示販売 |
| 10月30日「きみどり会」の作品展がメインの「わいわい祭り」 | ||
| 椿 窯 | ||
交通アクセス
 |
||
| 右が主の上田達生さん | ||
| 登り窯 | 登り窯で焼いた作品 | 陶びな展会場入り口 |
| 陶びなの段飾り | 絵の方にも造詣が深い | 陶びなの親王飾り |
| ガス窯 | 敷地内に有る椿の珍木 光市の名木百選の一つ |
愛犬のフレンチブルドック |
| 焼酎サーバー定価1万円のところを特価7千円で手に入れた。 サーバーの作は勿論上田氏、下の木製の台は田布施の合歓の木工房、そして蛇口は伊保木の光井鉄工所製ときている。 左党からの注文が多く、2週間待ちであった。 サーバーには、上田氏が飲み屋で恩師礒永秀雄先生と出会ったときに書き留めておいた詩が書いてある。(下参照) |
||
| 今回購入した雛の絵。 これで1500円也。 |
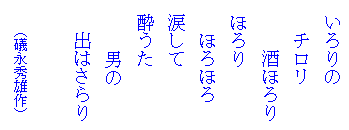 |
|
| 8月に家を全焼し、ようやく片付けが済み、地鎮祭にこぎつけた椿窯。 10月29日にはフォークの仲間や多くの支援者が駆けつけ、盛大に祝ったという。 多くの財産を燃やし、しょ気ているかと思いきや、益々製作意欲を増しているというから、上田氏もすごい人である。 |
||
椿祭り
| 5月の最後の土・日である27・28日に椿祭りがあった。 椿窯が再建されて、初めての大きな催しとなり、雨模様の天候だったにもかかわらず、沢山の人が訪れていた。 左写真の奥の黄色い建物が新たに再建した「光の海舎」と名付けられた展示場兼住居である。 今回の椿祭りは地元の3つの窯元が中心ではあったが、沢山の協賛店が出店していた。 毎年のことながら、今回も焼酎のコップを購入しておいた。 |
||
| 「光の海舎」の玄関 | 1階の展示物 | 1階の展示物 |
| 1階の展示物 | 2階の展示物 | 2階の展示物 |